~~~島根県飯石郡吉田村発~~~


第3回「鉄の歴史村フォーラム」
1・近代たたら操業 H14.11.15~16
残念ながら途中で終了しました。(T-T)
2・たたらフォーラム H14.11.17
午前中は窪田蔵郎さん、野原健一さんの講演、
午後は参加者による討論会です。
3・鉄の未来科学館特別展 現代の自動車エンジンにおける合金(開催中)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
新方式の小だたら・小学生操業体験はこちら
近代たたら操業
一緒に作業に参加した皆さん、お疲れ様でした。
終了しました。途中で。(TT)
今回は、第1回のときよりも惨憺たる結果でした。
製鉄作業の標準化を目指しましたが、いろいろな部分で
統一できていないところがあり、課題を残すこととなりました。
次の操業では、いい鉧ができるといいですね。
次回操業されれば。ですが。・・・( ̄  ̄;) うーん
比べてみよう。d(>_< )



左は2000年。 中は2001年。 右は2002年
中は成功した操業のときの炉底部分。両端は失敗の際の炉底部分。
何か気付く事はないでしょうか?
羽口前の火球は約5寸。この範囲内に対面の壁が入ると、土を炙ってしまい、
炎の色が変わります。これが今回の決定的な失敗の原因ではないかと考えます。
羽口前が狭くなっていると、風の当たる炭の量が少なくなり、発生する
カロリー量も少なくなります。その為に、炉底部分の温度が上がりにくくなると
考えられます。この辺を考慮すれば、単純なV型の炉底形状が、理にかなった
形である事がわかりますねぇ。さて、次回はどんな設計になりますでしょうか。
次回操業されれば。ですが。・・・( ̄  ̄;)
以上、鍛冶大たたらの「余計なお世話的考察」でした。
なお、この考察に関わる意見、苦情等は受け付けません。ヾ(・・;)



今年は少なめですな。(^_^;)

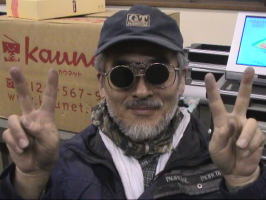

うっ・・・・・・・・



毎年恒例、居眠りコーナー。~(^^~)(~^^)~
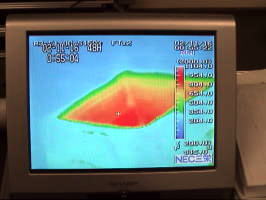
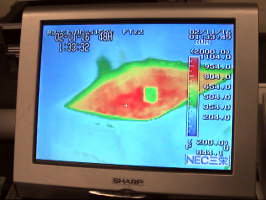
サーモグラフの画像。 右側、冷えた炭が1個入りました。(゚ロ゚〃)



またのろを出します。



こんな火の出るときもありました。



食料は豊富!!! (ノ^^)ノ



とりあえずは腹ごしらえと燃料?補給。d(>_< )



しかし操業は続きます。



さーて、どうしましょう・・・・・・・



まだ火が戻りません。(TT)



詰まってきた邪魔物を取ります。



火の色がおかしいです。



今回も怪しい新兵器が登場。・・・(TT; )( ;TT) オロオロ



11/15 操業開始です。d(>_< )


後は操業まで乾燥させます。



羽口あけ作業。 さて!種付け馬本領発揮。d(>_< )



船底型に突き固めます。



下枠を置き、土を入れます。



炉下部を作ります。まずは灰すらし。



11/13 子供たちが小だたらの炉作りを体験。(・~・)



地元ケーブルテレビの取材風景を取材。(^ー^)



11/12 今日は炉底乾燥のみ。



今年もこの虫が・・・ハッ∑(゚ロ゚〃)



炭を切り、炉底を乾燥し、砂鉄を準備。


11・11 準備開始です。(>_<)9
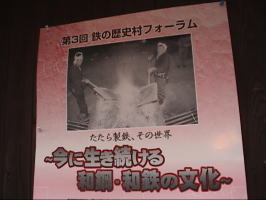
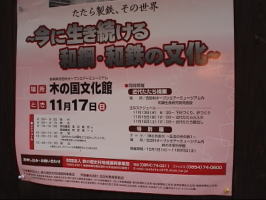
DVTR撮影(13日以降分):柳楽晴美(迷?)カメラマン (^_^;)
お問合わせは(財)鉄の歴史村 [ 0854-74-0311(代) ]へ。
ホームへ